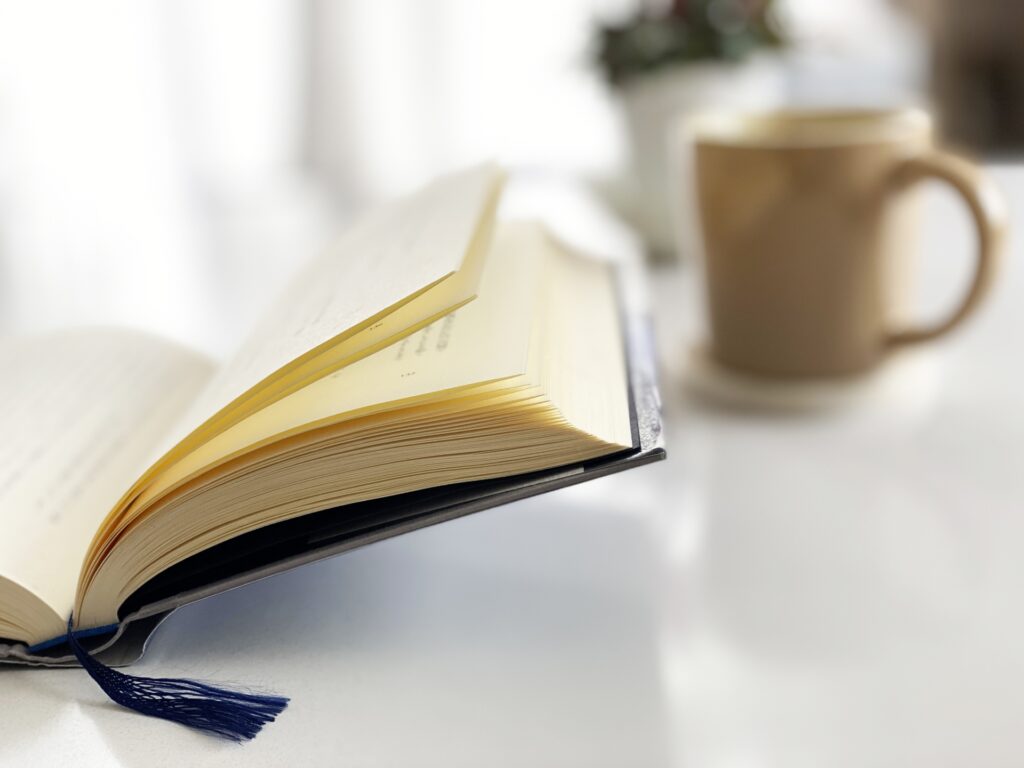
学びのための、本の読み方
「読み」の整理学 外山 滋比古 (著)
なぜ「読み方」を見直す必要があるのか?
投資の勉強をしようと思って本を読む。でも「読んでも頭に入らない」と感じたことはありませんか?
難解な理論や難しい専門用語などが出てくると、より頭に入りにくく感じるものです。しかし、この「読みにくさ」の理由こそが、真の学びのヒントだということが本書は教えてくれます。
今回ご紹介する外山 滋比古氏の『「読み」の整理学』は、私たちが普段無意識に行っている「読む」という行為を深く掘り下げ、真の学びとは何かを教えてくれる一冊です。
特に、難解な経済・金融の知識を学び、実生活に活かしたいと考える方には、必読のヒントが詰まっています。
この本で提唱されている二つの「読み」のタイプを知ることで、あなたはお金の学びをより深く、そして効果的に進めることができるでしょう。
知の境界線:「アルファ読み」と「ベータ読み」とは?
著者は、「読む」という行為を以下の2つに分類しています。
- アルファ読み(既に分かっていることを読む)
- 自分の知識の範囲内で内容を理解し、確認しながら読むこと。(例:知っている用語の復習、共感できるエッセイを読むなど)
- 【問題点】 楽でスムーズですが、新しい「考える」機会が失われやすい。
- ベータ読み(知らないことを読む)
- 難しい専門用語や概念に直面し、労力をかけて意味を掴み取ろうとすること。(例:専門的な経済学の論文、難解な金融商品の解説書を読むなど)
- 【重要性】 未知との遭遇であり、真の知識習得と論理的思考力の向上に繋がる。
お金や投資の学習への応用?
私たちが「難しい経済ニュースは後回し」「投資は専門用語が多くて挫折した」と感じる時、それはベータ読みを避けてアルファ読みだけで対応しているサインなのかもしれません。
でも、実際に新しい知識を与えてくれるのは、ベータ読みであることがわかります。
難しいことや知らないことを避けようとせず、あえて立ち向かい、理解しようとする。そこにこそ、本当の学びと知的な成長がある、と著者は説きます。
読解力の本質:わからなくても立ち止まる「試行錯誤」の重要性
私たちが学校で教わった時代よりもずっと昔の教育は、「意味がすぐには理解できなくても、字面から入っていく」というアプローチをとっていたと言います。
いわゆる寺子屋などで行われていた「漢文の素読」といったアプローチです。
本人が意味をよく理解していなくても、ひたすら文字を音読し、それを繰り返す中で後に意味を理解させていくという教育方法です。
実はそこに、ベータ読みの本質を見ることができると著者は考えています。
現代の教育や学習では、「理解できない文章は文章が悪い」と捉えられがちで、著者自身もそれを直に経験したエピソードも本書に書かれています。
ベータ読みとは、わからなくても、「どういう意味だろう?」「この言葉の定義は?」と立ち止まり、考え、他の情報と照らし合わせたり試行錯誤して理解しようとすることこそが、知識を定着させ、あなたの血肉とする学びのプロセスだということです。
3. 最後は「読んだ人」が意味を完成させる
この書籍の最も心に残るメッセージの一つが、「本は、書いた人のものではなく、読んだ人のものでもある」という考え方です。
同じ本を読んでも、20代の独身の方が読むのと、50代で読むのとでは、共感する部分や、重要だと感じる情報が変わってきます。
私自身も、同じ本でも10年前に読んだ時と、今読んだ時では、また違った内容に感じられることがあります。
今の生活の背景にあるもの、10年間で身に付けた知識や経験、そういうものが積み重なって、本の内容は変わっていくようになる。
本というものは、書いた人が中心にいるのではなく、読む人が中心にいるという事がよくわかります。
結びに:本を読んで「考える」習慣を
『「読み」の整理学』は、「読む」というシンプルな行為の奥に広がる、深く、広い思索の世界を私たちに示してくれました。
私たちは、ベータ読みを通して真の学びを得ることもあるという事実。
本をたくさん読むための、斜め読みや速読といった技術とは、まったく逆の世界です。
これまで、たくさんの本を読めば読むほど、知識や知恵がつくようになると思っていましたが、そうではないのかもしれません。
たとえたくさんの本を読めたとしても、それがアルファ(知っている知識の世界)読みだけで読んでいたら、自分の中の世界は広がっていかない。
この本は、そのことを気づかせてくれました。