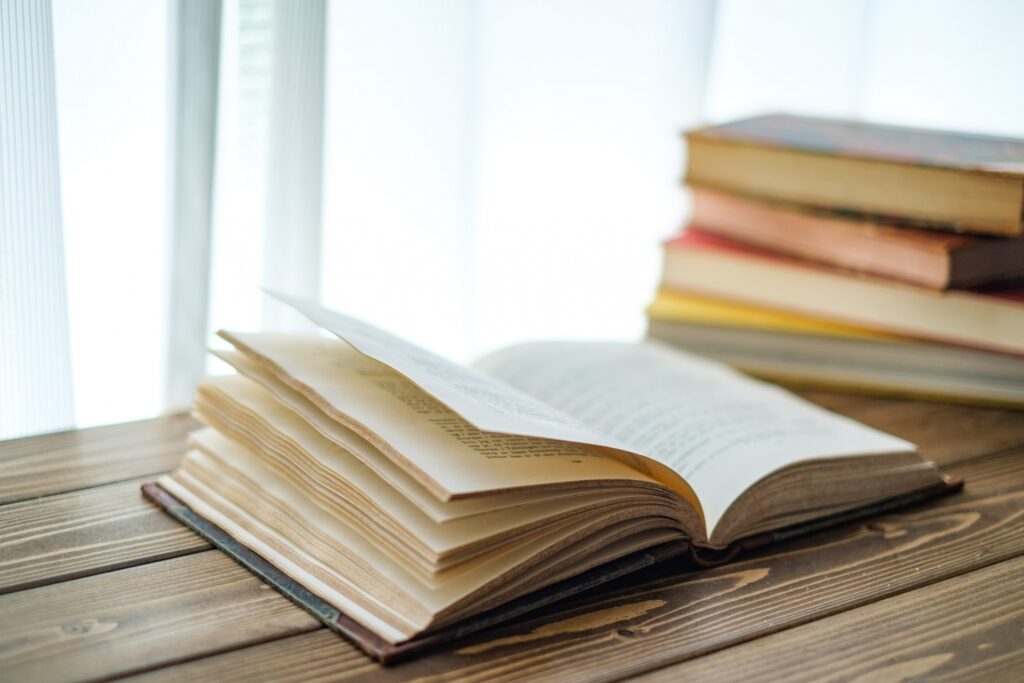
読解力という大切なスキル!
『AIに負けない子どもを育てる』 著者:新井 紀子
💡 はじめに:AIブームの裏側にある「私たちの致命的な弱点」
AI時代が到来し、「AIが私たちの仕事を代替する」「AIを使いこなせば勝てる」といった言葉が飛び交っています。
しかし、そもそもAIとは何者なのか? 私たちは本質を理解しているでしょうか?
今回ご紹介する新井紀子氏の著書『AIに負けない子どもを育てる』は、前作に続き、AI研究の第一人者である著者だからこそ発見できた、現代人の根深い問題点を突きつけてきます。
本書を読むと、AIが凄いのではなく、「現代人の能力の低下」こそが、AIに仕事を奪われる最大の要因だと痛感するでしょう。
この記事では、AI時代を生き抜くために不可欠な「考える力=読解力」の本質に迫ります。
1. AIへの誤解を解く:「考えることができない」数学的世界
AIへの世間的なイメージでしか考えていない人にとって、本書の冒頭は目から鱗が落ちる内容です。
- AIは思考しない: AIは、私たちの脳とは異なり、数学的な観点から作られています。確率や統計を利用しているため、少なくとも現段階のAIには「物事を考える力」は根本的に備わっていません。
- 認知も人には敵わない: 考える以前に、AIは「認知」という作業さえ人に及びません。例えば、写真に車が写っていることをAIに認識させるには、膨大な数のデータ解析が必要です。なぜなら、AIは車の概念を理解しているのではなく、境界線を判別する確率を上げているにすぎないからです。
AIは所詮「数学の世界」から出ることができない存在であり、人のように「認知したり、考えたりする」ものとは全く別物だと、著者は明確に説明します。
2. 「文章が読めないAI」と「読解力が低下した現代人」
AIは、選択問題のように確率的に正しい選択肢を選ぶ作業は得意ですが、東大入試のような「考える」ことを重視した問題には対応できませんでした。
なぜなら、「考える」ことの根本には、「文章を読んで理解する」という能力が不可欠だからです。
しかし、著者の研究によって、現代人の多くがこの「文章を読んで理解する」という能力が、AIの確率と統計に基づく結論、つまり考えるまでもない基礎的な答えにさえ劣っているということが判明しました。
実際に本書の例題を解いてみると、「自分には読解力がある」と思っていた人でも、「あれ?」と立ち止まってしまう箇所があるはずです。
つまり、AIが進化しているのではなく、「考える能力が、人がAIに負けるほど、落ちてきている」というのが、この問題の大きな要因だと著者は警鐘を鳴らしています。
3. 【最も大切な自己投資】読解力こそ、AI時代の最強の武器
「文章を読んで理解する」能力は、AIには原理的にできません。
つまり、この「読解力」こそが、AIに負けない私たち人間の最大の強みとなるのです。
本書が伝えるのは、学校のテストで高得点を取るための「暗記」や「詰め込み」学習ではなく、「教科書を読んで、本当の意味で理解する」という、考える力を身につける学習の重要性です。
そして気になるのは、「自分に高い読解力があるのか?」ということでしょう。
- 教師だからある? 本を読んでいるからある? → いいえ、見当違いです。
本書には、自分の読解力を客観的に確認できるリーディングテストの体験版が付いています。ぜひ、このテストでご自身の読解力が、東大に合格できるレベルの「考える力」に繋がっているのかどうか、実感してみてください。
4. まとめ:「高いレベルの読解力」が未来の資産になる
AI時代を生き抜くために、私たちに必要なのは、AI技術を追うことよりも、「人間にしかできない考える力=高いレベルの読解力」を徹底的に磨くことです。
読解力の向上は、子どもの学力向上はもちろん、金融情報の真偽を見極める判断力や、複雑なビジネス環境を理解する洞察力といった、「未来の資産」を育むことと同義です。
本書を読むことは、AI時代を生き抜くための、最もシンプルで効果的な自己投資となるでしょう。