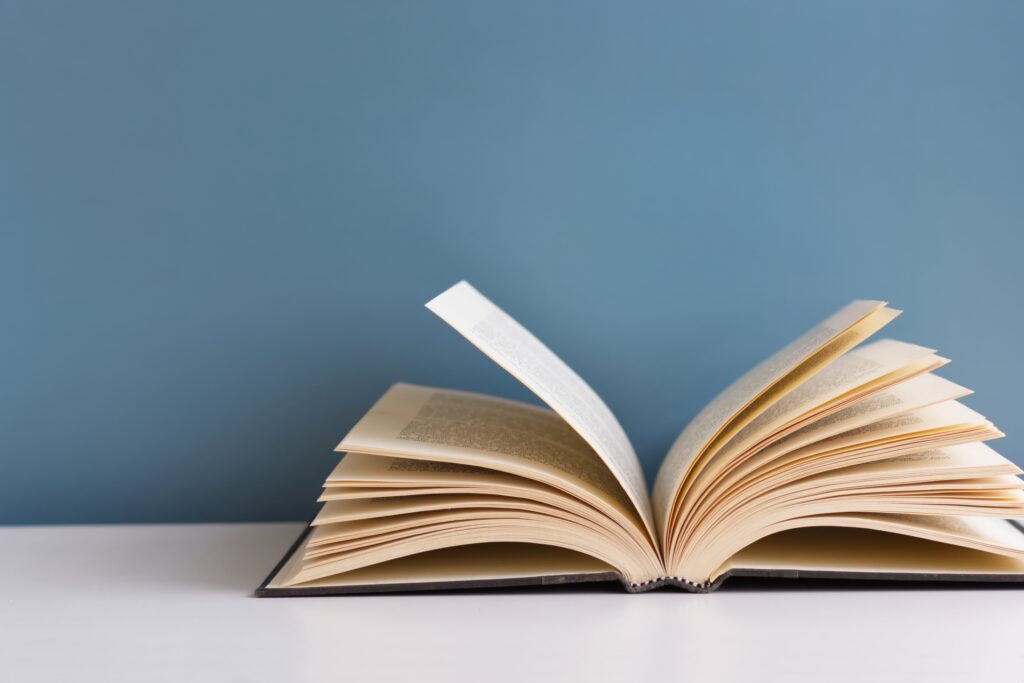
眠るって、実は不思議なこと?
『睡眠の起源』 金谷 啓之 (著)
人生の3分の1を占める「睡眠」。なぜ私たちは無防備になる必要があるのか?
「寝ないと健康を害する」と誰もが知っていますが、逆に「なぜ、私たちは無防備になる睡眠という状態を必要とするのか?」を深く考えたことはありますか?
人類や動物は、進化の過程で、生存に不利なものは削ぎ落としてきました。にもかかわらず、外敵に襲われるリスクを伴う「睡眠」という無防備な状態は、なぜ今もすべての生き物に存在し続けているのだろうか?
寝ないで活動できれば、より人生を豊かに使えるはず——。
そう考えるのは当然かもしれません。
本書『睡眠の起源』(金谷 啓之 著)は、「脳の休息」という一般的な常識を覆し、「脳のない生物も眠る」という驚きの事実から、私たちが当たり前と考えている「睡眠」の正体に迫ります。
1. なぜ人類は「無防備な睡眠」を捨てなかったのか?
自然環境で生きることを考えれば、睡眠は極めて危険な状態です。
- 肉食動物に襲われる
- 外敵からの攻撃に対応できない
- 逃げ遅れる
進化論から見れば、このような「無防備になる時間」は、真っ先に淘汰されるべき不必要な要素だったはずです。
著者はこの疑問を深く掘り下げます。
何億年もの時をかけ、不必要なものを削って進化してきた私たち。それでもなお「睡眠」という時間を削ることができなかったのは、睡眠が、生き物にとって生命維持に欠かせない、何か根源的な目的を果たしているからに他なりません。
その答えを探る旅が、本書のテーマとなっています。
2. 人生の3分の1を占める「睡眠」の正体とは?
私たち人間は、人生の約3分の1を寝て過ごします。
しかし、そもそも「寝ている」とはどういう状態なのでしょうか?
- 目をつむっている時?
- 意識がない時?
- 動きがほどんどない時?
睡眠には、脳が活発に動くレム睡眠や、深い休息状態であるノンレム睡眠など、複数の状態があることもわかっています。
最近ではスマートウォッチなどで睡眠状態を計測できるようになりましたが、私たちが思っている以上に「睡眠」の概念は奥深く、その定義は難しいものです。
これまでは一般的に、睡眠は「脳を休ませるための時間」であり、その間に情報や記憶を整理していると言われてきました。つまり、「脳があるから睡眠をとる必要がある」と考えるのが定説でした。
しかし、本書は、この常識を覆す驚きの真実を提示しています。
3. 「脳がない生き物も眠る」?常識を覆すヒドラの研究
著者が研究対象とした『ヒドラ』という生物は、私たち人間とは異なり、脳という臓器を持っていません。
定説通りであれば、脳がないヒドラは「睡眠」をとらないはずです。
しかし、ヒドラを観察した結果、まるで寝ているかのように動きが少なくなる時間帯があることが判明しました。これは、単に活動が低下しているのではなく、「睡眠状態」と呼べるような、特有の現象であることがわかってきたのです。
この発見は、「睡眠=脳の休息」という私たちの持つ常識に強烈な一撃を与えます。
「睡眠」とは、脳といった特定の臓器の活動状態によって決まるものではないとすれば、一体、生物の何を休ませているのでしょうか? そして、なぜ存在するのでしょうか?
本書は、脳の有無にかかわらず、生物が生命を維持するために必須な「何か」が、睡眠という現象の起源にあることを示唆しています。
4. 本書の究極のテーマ:「意識とは何か」の謎へ
『睡眠の起源』は、著者自身の長きにわたる研究人生と共に、睡眠にまつわる数々の不思議を解き明かしていきます。
そして最後に、この研究の先にある究極の問いへと読者を誘います。
それは、これまでの科学の歴史の中でも、いまだに答えを得られていない「意識とは何か」という最大の謎です。
睡眠という根源的な現象を理解すること。それこそが、人類が持つ「意識」の解明へとつながる——。
本書を読むことは、私たちの日常に深く根差す「眠り」という行為を通じて、生命や意識といった壮大なテーマに触れるロマンに満ちた体験となるでしょう。
まとめ:あなたの睡眠観が変わる一冊
『睡眠の起源』は、私たちが当たり前と考えている「睡眠」という現象を、生物学、進化論、そして哲学的な視点から深く見つめ直すきっかけをくれます。
- 無防備な睡眠が淘汰されなかった理由
- 脳の有無にかかわらず生物が眠る事実
- 睡眠が持つ、意識の謎に迫る可能性
寝ても寝ても疲れが取れない、といった「お金」に影響する健康の問題を抱える方にも、ぜひ読んでいただきたい一冊です。
興味を持たれた方は、ぜひ本書を手にとって、科学がまだ知らない「睡眠」の謎を解き明かす旅に出かけてみてください。