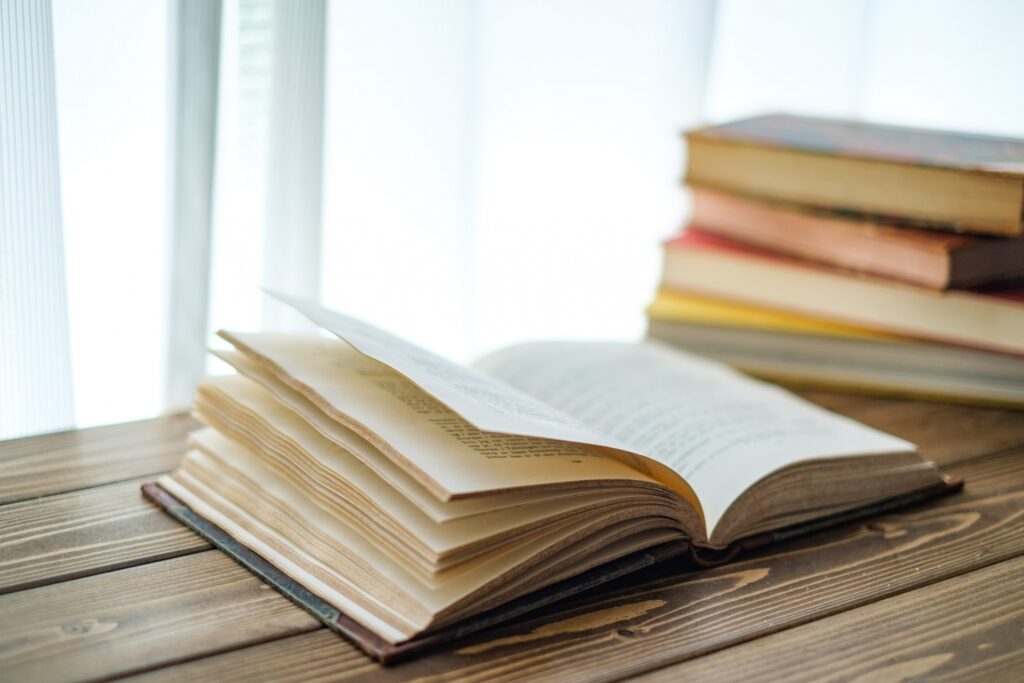
食欲って不思議だ!
『食欲人』 デイヴィッド・ローベンハイマー (著), スティーヴン・J・シンプソン (著)
1. 「食欲の不思議」:人間はなぜ食べ過ぎてしまうのか?
「お腹が空いたから食べる」「もうお腹いっぱい」。あまりにも単純に捉えてきた「食欲」という本能。
昆虫学から始まった本書の研究は、バッタ、マウス、ヒヒ、そして人間まで、多くの生き物の食欲が「タンパク質」という単一の栄養素によって強くコントロールされているという驚くべき真実を明らかにしました。
📌 食欲コントロールの真実
- 生き物の本能: 多くの生き物は、食事のタンパク質比率が低いと食べる量を増やし、常に一定量のタンパク質(タンパク質欲)を摂取しようとします。
- 満腹のメカニズム: 血液中の糖分や胃の容量ではなく、タンパク質欲が満たされるまで食べ続けることが食欲の主要な駆動力になっている、というのです。
野生の動物たちが、誰にも管理されず、本能のままに食事をしているのに、生きていくのに必要な栄養素がちゃんと取れているのはなぜなのか?
その答えが、この「タンパク質欲求」にありました。
2. 超加工食品が引き起こす「食欲のバグ」と肥満のメカニズム
野生の動物にはできるのに、なぜ人間は、本能的な食欲コントロールを失い、食べ過ぎによる肥満や、生活習慣病に苦しむようになってしまったのでしょうか?
著者は、その背景に、短期間で劇的に変化した「食の環境」、特に「超加工食品」の存在を指摘しています。
超加工食品(長期保存可能、着色料や香料で味・食感・香りを強化した食品)は、安価に美味しく作るため、高価なタンパク質や食物繊維を減らし、代わりに安価に手に入る炭水化物や糖分に栄養が偏る傾向があると指摘しています。
- 味覚と栄養の乖離: 本来、塩味や旨味を欲している時は、身体がタンパク質を求めているシグナルである可能性があります。
- 食欲のバグ: ポテトチップスのように、調味料で塩味や旨味を強くした炭水化物過多の超加工食品を選んでしまうと、味覚ではタンパク質を摂取しているのに、身体には「タンパク質が足りない」状態になってしまうので、より多くのタンパク質を摂取しようとして、ポテトチップスに含まれる炭水化物やカロリーを過剰に摂りすぎてしまうようになる。
3. 健康と家計を守るための「タンパク質比率」
この研究が示唆するのは、健康的な食事とは「何を食べて、何を食べないか」という極端な制限ではなく、古くから言われる『バランスの良い食事』、特に「炭水化物とタンパク質の適正な比率」に戻ることだと指摘しています
例えば、人間の理想的なタンパク質比率が15%だと仮定した場合、超加工食品中心の食事ではこれ以下の比率になっていることが多く、それが過剰な摂食と肥満に繋がるようになります。
この知見は、昨今話題のケトン食や低糖質ダイエットが成功する理由も、単に「糖質を減らす」ことではなく、結果として「タンパク質比率の高い食事になり、食欲が自然に抑えられた」ことによるものだった可能性を示しています。
4. ライフプランに直結する「食」のマネジメント
食欲のコントロールを失い、肥満や病気になることは、医療費の増大や将来の健康リスク、ひいては老後資金の不安にも直結する話でもあります。
本書は、私たちが本能に頼るのではなく、「超加工食品」という現代の罠を理解し、意識的に食事のバランス(特にタンパク質比率)を管理することの重要性を教えてくれます。
「食欲」という最も身近な本能をマネジメントすることこそが、健康、そして家計を守るための、最も基本的で重要なライフマネジメントスキルなのかもしれません。