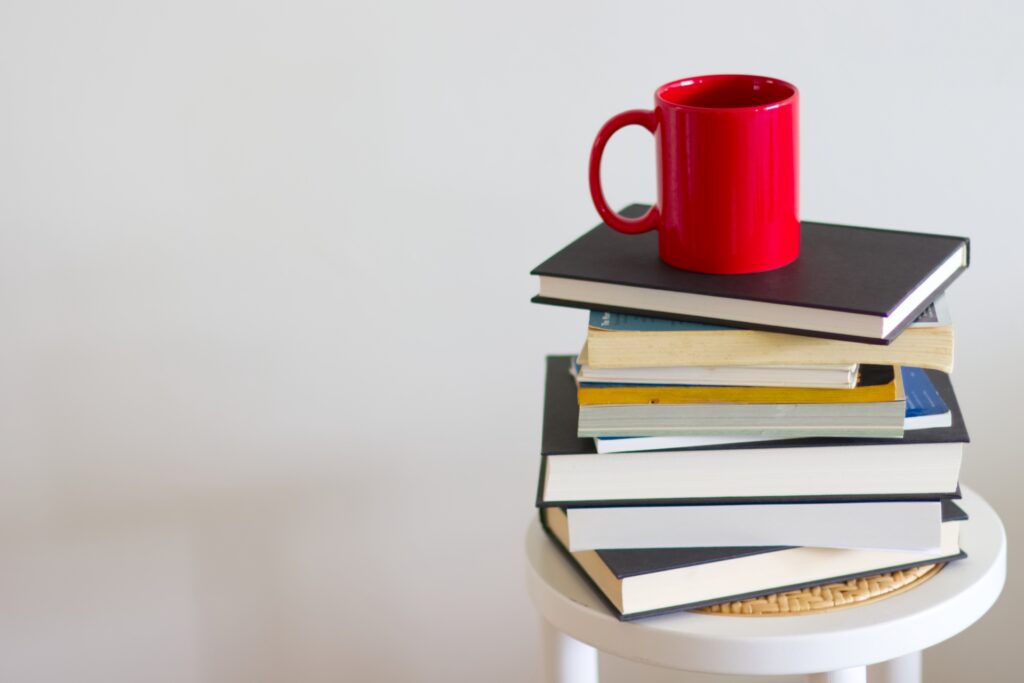
常識に捉われるな!
『わが子と考えるオンリーワン投資術』 ジョン・モールディン (著)
この本に登場する人物たちは、みんなただの理論家などではなく、現実のマーケットで実際に成功を収めてきたプロの投資家たちです。
つまりは、実務の中で優秀な成績を上げてきた投資家たちが考える、投資とマーケットの真実が、この一冊に詰まっています。
10人の投資家たちによるアドバイスは、どれも非常に貴重です。投資初心者の方だけでなく、経験豊富なベテラン投資家であっても、新たな気づきを得るための大きな参考になるでしょう。
たとえば、超長期の債券への投資が、株式投資以上の利益をもたらす可能性。
リスクはリターンを得るための絶対条件ではないという話。
時価総額加重平均型のインデックスへの投資は、実は効率的な投資法ではないものであること。
これらの話は、誰もが信じる投資の常識でもある、「債券は株式に劣る」「リスクを負うほどリターンが得られる」「インデックスファンドが最善」という常識が、実は間違っているということを教えてくれます。
この本から学べることは、常識に囚われている私たちにとって、まさに「目からうろこが落ちる」体験となることでしょう。
債券は株式に劣る?
本書に登場する債券投資家のゲーリー・シリング氏によると、1981年から2005年の約25年間は、S&P500指数への株式投資よりも、25年満期のゼロクーポン国債に投資をしていた方が、リターンが数倍高かったと述べています。
債券投資に関して一般的に言われるのは、「債券のリターンはインフレ率以下になる可能性が高く、主な投資先としては株式に劣る」という話です。
しかし、実際のデータを見ると、常に株式が債券に勝っているわけではありません。
少なくとも、高インフレから低インフレへ移行した1981年から2005年の時代は、シリング氏のパフォーマンスが示す通り、株式投資よりも債券投資の方が有利だったことがわかります。
この期間は、インフレ率が収束したことで金利が低下し、債券価格が上昇するという、債券投資に非常に有利な環境でした。
しかし投資の現場では、いくら債券に有利な投資環境であるとはいっても、それでも債券よりも株式の方が投資のパフォーマンスは上という考え方が一般的だったようです。
そのため、シリング氏が「債券投資の有効性」を主張しても、賛同する人はほとんどいませんでした。
しかし、シリング氏は自分の考えを変えることなく、債券投資を重視した運用を貫徹します。
その結果、彼の投資は報われました。株式よりも債券がリターンで上回り、シリング氏は大きな資産を築いたのです。
一般的な意見に流されず、自分の考えを突き通した意志の強さこそ、まさにプロの投資家だと感じました。
この章では、常識に捉われないという事の大切さを考えさせられました。
リスクとリターンの関係は、絶対の条件ではない?
一般的に投資というのは、ハイリスク・ハイリターン、ローリスク・ローリターンという関係で成り立っていると説明されています。
しかし、投資の現場を深く観察すると、このリスクとリターンの関係性が、常に絶対の条件ではないことがわかります。
たとえば、現金、債券、株式などが斜めに並ぶ「リスク・リターン図」は金融商品の説明でよく見かけますが、実際のマーケット感覚とは乖離していると感じることも少なくありません。
そもそも、本書に登場する投資家を含め、現実のプロ投資家たちが目指すのは、「できるだけ損をせず、できるだけ大きな利益を得る」、つまり『リスクを抑えながらリターンを得る』という投資を理想形としているのではないかと思われます。
もし本当にリスクとリターンが常にきっちり比例するなら、銘柄選定や投資先の分散といった投資家の努力や工夫は、すべて無意味になってしまうでしょう。
では、なぜそこに「絶対的な関係性がある」という考えが広まったのか?
その背景には、金融業界で現代ポートフォリオ理論(MPT)が広く普及したことがあると説明してます。
この理論がリスクを「価格変動のブレ幅」だと定義したことで、本来の「お金を失う可能性」というリスクの本質的な視点からかけ離れてしまったのではないかと言っています。
たとえば、バリュー投資家(本質的価値に比べて割安な株式を探す投資家)のスタイルは、MPTの根本である効率的市場仮説とは相反しています。
彼らは、お金を失うリスクを極力減らしながら、最大限のリターンを追求する、「ローリスク・ハイリターン」を努力と工夫で実現しようとしています。
果たして、彼らの「価格変動リスクと期待リターンを切り離して考える」手法は間違っているのでしょうか。
学者たちがリスクを「価格の振れ幅」と定義したことで、本質的な「お金を失うリスク」と「期待リターン」の関係性がかえって分かりにくくなってしまったのかもしれません。
本書を読んだことで、私自身も「リスク」や「期待リターン」という言葉を、正しく定義して使えていなかったことに改めて気づかされました。
インデックス投資の常識を覆す?「時価総額加重平均型」は市場リターンを約2%損している。
今では資産運用の常識ともいえるインデックスファンドのほとんどは、時価総額加重平均型と言っても過言ではありません。
この時価総額加重平均というインデックスは、インデックスファンドを世に広めたジョン・ボーグル氏も推奨しており、S&P500やTOPIXなど、主要なインデックスの多くが採用している算出方法です。
しかし、本書に登場するロブ・アーノット氏は、投資において時価総額加重平均型は正しい選択肢ではないと主張します。むしろ、この方式に投資することで、投資家は株式市場の本来のリターンから約2%程度を損しているという意見を述べています。
なぜなら、時価総額加重平均型は、市場価格の歪みを反映しやすいからです。
時価総額が大きい銘柄は、すでに適正価格を超えた株価となっている可能性が高く、逆に時価総額が小さい銘柄の中には、適正価格以下の株価になっているものが含まれている可能性が高いからです。
つまり、時価総額加重平均型は、割高な銘柄の比率が高く、割安な銘柄の比率が低くなるという傾向があり、そのため、このインデックスファンドは決して効率的とは言えず、結果として市場リターンを約2%損しているという結論になるわけです。
この2%の損失を取り返すための代替案として、アーノット氏は均等ウェート型のインデックスファンドへの投資を推奨しています。
実際、S&P500の銘柄に均等ウェートで投資を行うファンドが、時価総額加重平均型のものより高いリターンを出している例は、広く知られています。
〔参考:383A:MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信〕
理論を超え、現実の投資家が示す「お金の真実」
「理論」と「現実」は違う。 本書を読み、アカデミックな理論家と、実際のマーケットで成功を収めてきた投資家の見ている世界が、いかに異なるかを痛感させられました。
本書では、先に紹介した債券やインデックスの話だけでなく、投資と心理、ビジネスとお金、金持ち投資家の実像、そして複利の真の力など、多岐にわたる重要なテーマが語られています。
そして、ただ知識として知っているだけの知識人から学ぶアドバイスと、実践の現場で結果を出してきたプロから学ぶ言葉とでは、その重みが全く違うのを感じます。
この本に登場する投資家たちは、短期トレーダー、債券専門家、ファンドマネージャー、ビジネス成功者など、多様なフィールドで実際に利益を得てきたプロフェッショナルばかりです。
彼らの言葉一つひとつに、深い洞察とリアリティが込められているのを感じます。
多角的なプロの視点から、資産形成の普遍的かつ本質的なポイントを紹介している本書は、まさに貴重な一冊と言えるでしょう。