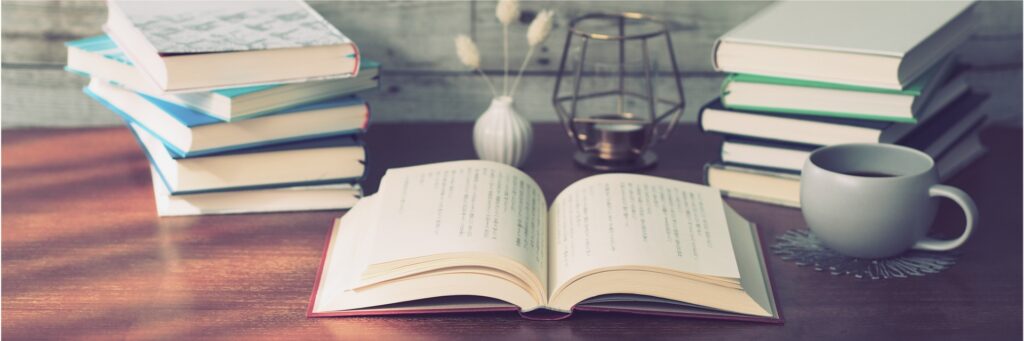
お金よりも大切な事?
お金の不安という「幻想」
「将来のためにお金を貯めなければ」「投資や資産運用を始めなければ」――そう考えている人はとても多い反面、「もっとお金を稼ぎたい」と思っている人は、意外と少ないのかもしれません。
少し前までは、お金は「稼ぐもの」という意識がもっと強かったように感じます。良い仕事をして価値を提供することで、それに見合ったお金を手に入れることができる。だから、しっかり働くことが、お金を手に入れるための最善の方法でした。
しかし、今の社会はお金は「稼ぐもの」ではなくて、「貯めるもの」となり、そしていつしか、投資で収入を得ることが、効率的にお金を手に入れるための手段だという考え方が、当たり前のように広まってきました。
FIREという言葉も流行し、早く資産形成して、投資の収益で生活できるようになることが人生の目的だと語る人も増えています。
また、NISAやiDeCoといった資産形成制度の強化や、政府の金融教育推進の流れもあり、世の中的にもそれが求められている雰囲気すらあります。
本書のテーマとなっているのは、そんなお金至上主義の世の中に対する疑問。そして、お金が物事の中心となっていることで生まれている得体のしれない不安感。
みんなを何気なく貯蓄や投資に向かわせている元凶でもある「お金の不安」。その原因は一体何なのでしょうか?
「彼を知り己を知れば百戦殆(あやう)からず」という孫子の言葉にもある通り、ただ不安だと言うだけでなく、その不安を感じさせている「敵」は何なのかを知ることが必要だと、この本の著者は説いています。
働く人が強くなる時代へ
お金というのは、価値を交換するための道具です。
お金があることで、私たちは自分の得意な事に集中できるようになり、社会はより効率化されるようになりました。
例えば、私たちが生きていくためには、まず食事をしなければいけません。動物や魚を捕まえたり、米や野菜を育てたりするなどして食料を手に入れる必要があります。
このとき、動物を捕まえるのが上手な人、魚を捕まえるのが上手な人、米や野菜を育てるのが上手な人、それぞれがそれぞれの得意分野に集中する「分業」ができるようになったことで、この世の中は効率的になってきました。
その分業によって各自が生み出した価値を、互いに交換し合うための「間を取り持つもの」が、お金の本来の意味です。
つまり、本来ならば「仕事(価値提供)があって、お金(交換の道具)がある」というのが順番として正しかったはずです。しかし、今の世の中は、お金が先になってしまってはいないだろうか、というのが著者の問いかけです。
お金を手に入れることが目的となり、そのために仕事をしている。お金さえ手に入れれば、なんでもできるようになると思っている人も少なくない。
しかし、現実はそうではありません。お金というのは、物やサービスを「売ってくれる人」がいて初めて意味があるのであって、その物やサービスを提供する「人」がいなくなったら、お金には何の価値もなくなってしまいます。そしてそれは、決して昔話などではなく現代においても同じことのはずです。
つまり、本質的には、お金よりも、働いている人の方が強い。これが経済の本来の在り方なのかもしれない、というわけです。
よく考えてみれば、それを実際に体験したことがある人というのは、結構いるのかもしれない。
この本の著者は、お金があっても売ってくれる人がいなければ意味がないという経験を阪神淡路大震災で体験し、私個人も東日本大震災で物流が滞り、ガソリンスタンドではガソリンが少なくなり、コンビニでは一部の商品がなくなっていることもありました。どんなにお金があっても、物が買えない状態になるというのは、確かに経験をしていました。
そうなると、お金さえあればとだけ考えて、働くという本質的な価値の提供の意味を疎かにすることは、間違っていることなのかもしれません。
そして今、この日本では少子高齢化社会となり、だんだん働く人が減り始め、職種によってはすでに人手不足となっている時代に突入してきています。
この本の著者は、これから日本はお金を持っていることよりも、働くことの方が優位になる時代へ進んでいくのではないか、と提言しています。
投資家よりも起業家を育てる社会へ
NISAやiDeCoによって、多くの人が投資を始めるようになってきました。そして「貯蓄から投資へ」というスローガンもある通り、雰囲気的にも投資を推奨する流れができています。
ただ、その中で投資に関するある種の誤解も生まれてきています。それは、「株式投資をすると、経済の中心でもある企業のためになり、社会に貢献することができる」といった類のものです。
しかし、株式を売買するお金の流れでは、誰かが株式を買うために支払ったお金は、ほとんどのケースで企業には全く届いておらず、ただその株式を売った人の口座に入金されるだけになります。
つまり株式の売買では、企業の成長という価値に対しては、直接的にはなんの影響も与えていないということになります。
企業として株価が上がることは良いことだったとしても、株価が上がったことで新規事業や商品開発の資金になったり、新たに従業員を雇えたりといったお金には、直接関係がありません。
それに、株価が上昇して喜ぶのは、主に株主たちで、その会社で働いている社員は必ずしも喜んでいるとは限りません。
「株を買うお金があるなら、うちの商品を買ってもらった方がうれしい」というのが、社員たちの本音なのかもしれない。
まさに、投資ブームの裏側にあるものは、お金中心の価値観で、働く人の価値が後回しにされるという、ゆがんだ経済構造と言えるものなのかもしれません。
そしてこの経済構造の中で、この本の著者が主張しているのは、投資家が増えることよりも、新しいことを始めようという意欲のある人たちや、働こうという意識の強い人たち、そういう人たちを応援する世の中であるべきなのではないかと言っています。
つまり、起業家をもっと敬うような社会になっていかないと、いつまでたってもこのお金至上主義の社会から抜け出せないのではないかというわけです。
正直今の日本社会には、会社に勤めるのが当然で、自分で起業しようと考える人は、それほど多くないと感じます。むしろ、起業するという事に対して、不必要なほどの不安感を持つ人も少なくありません。
また、起業した人が成功をつかむという社会の雰囲気よりも、すでに大きな企業たちが、さらに強くなるという世の中となっており、自分で起業するより大きな会社に勤めてしまった方が楽という事もあるのかもしれません。
つまりは、今の日本社会は、『すでに持っているものが、より富むことになる世界』になっているというわけです。
そしてこれは、今の投資ブームについても同じことが言えます。
たとえNISAやiDeCoなどで非課税のメリットを与えたとしても、所詮投資というのは、すでに持っている者がより強くなっていく世界でしかありません。
たとえ株価がどんなに上昇したとしても、そもそもの投資額が小さい人にとっては、大した利益にもなりません。その反面、膨大な資金を投資している持っている人は、仮に少ししか株価が上昇しなかったとしても、その利益は莫大な富となる事があります。
わかりやすく例を挙げれば、100万円の年率10%は年間10万円にしかならないが、100億円の年率5%は、年間5億円になるという事です。
つまり、『金持ちがさらに金持ちになっていく世界』これが投資の世界というわけです。
お金至上主義の世の中では、こうなることが当たり前。だからこそ、お金よりも働くこと、新しいビジネスを始めること、そういうところにもっと焦点が当たってもいいんじゃないかと思うわけです。
この本を読んで、お金をたくさん持っていることよりも、働くという事をもっと尊重する社会の在り方の大切さをより感じるようになりました。