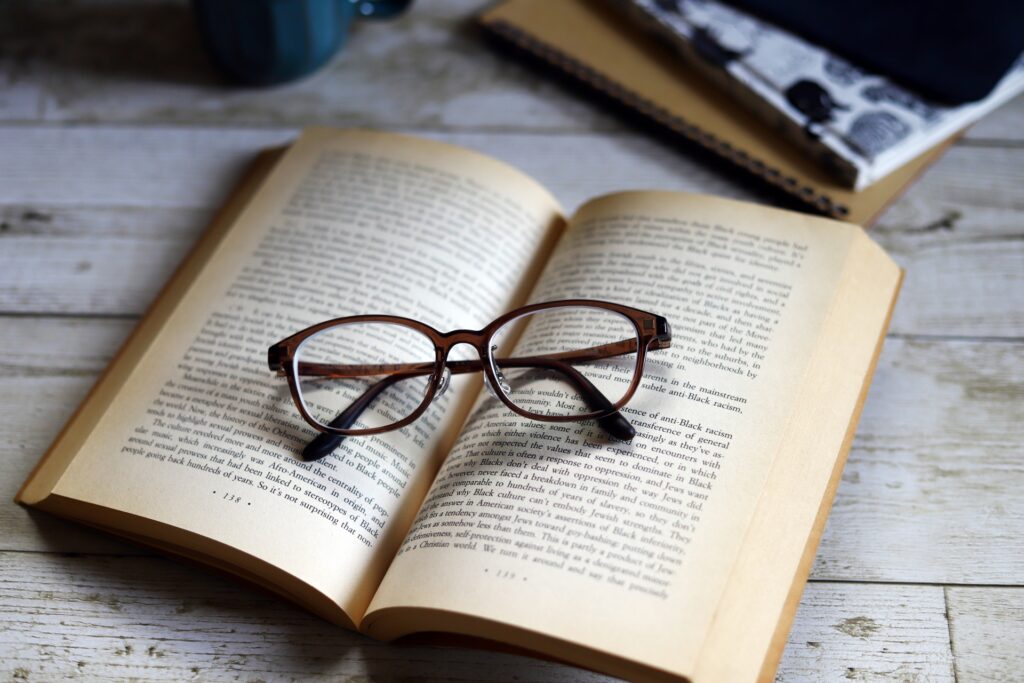
本を読んで行き着く答えは、同じところ?
『お金の名著200冊を読破してわかった!投資の正解』 タザキ (著)
本を200冊も読むなんて聞いたら、それだけでちょっとびっくりしますよね。特定の分野でこれだけの冊数を読み込めば、相当な知識が身につくはずです。
そういう私も、恥ずかしながら200冊以上の投資本を読んでいます。
そしてその中から感じたのは、多くの本を読み進めていくと、結論はだいたい同じところにたどり着くことになるのかもしれないということでした。
実は、今回読んだ『お金の名著200冊を読破してわかった!投資の正解』の著者の投資の考え方が、私が抱いていた投資観と驚くほど似ていました。
リスクの捉え方、リバランスの必要性、投資にかかるコストはできるだけ減らすこと、そして論理的な分析だけでなく市場心理も考慮に入れるべきだという点。
また、アセットアロケーションの考え方や、バブル、ブラックスワンといった話題まで、みんな私の投資に対するイメージとほぼ同じだったことにちょっとびっくりしました。
考えてみればそれもそのはずで、私がこれまで読んできた本が、著者が読破した200冊の中に含まれていたので、似たような結論に至るのは当然なのかもしれません。
言ってみればこの本は、私の投資に対する考え方を、そのまままとめてくれているような本だったと感じるぐらいでした。
ただ、投資に対する根本的な考え方は同じでも、最終的な運用手法だけは少し異なっていました。
この本の著者は「コア・サテライト投資」という運用スタイルを採用していました。
これは、安定した「コア(土台)」となる運用に、少し遊び心のある「サテライト(衛星)」運用を組み合わせるといった投資手法です。
私も、だいたいこれに近いコア・サテライト投資を行っていますが、コアとサテライトの扱いに若干の違いがあります。
著者の場合、コアの部分では低コストのインデックスファンドを活用し、サテライトの部分で個別株に投資しているとのことです。
一方、私の運用スタイルは、コアの部分で個別銘柄のパッシブ運用、サテライトには少し変わった投資信託やETF、時にはレバレッジを利用するなどして、かなりアクティブに運用するというスタイルを取っています。
もちろんどちらが正しいという答えはありません。
ただ、著者と私は、投資における「基準線」はおそらくほぼ同じものなのだと思いますが、具体的な「やり方」となると、そこにやはり個性が出てくるということなのでしょう。
「投資の正解」?、コアとサテライト
コア・サテライト投資のように、インデックスファンド以外に資産を分散させることは、リターンを減らすことになるだけだという主張も、また正しいと言えます。
それにもかかわらず、この本の著者も私も、現実にはサテライトでアクティブ投資を行っています。
もちろん、アクティブ運用がインデックスファンドに勝つ確率は低いというのは、私たちも知っています。それでもなおアクティブ運用を取り入れているのは、人間の「欲」や「本能」を理解しているからです。
当たる確率が低いと分かっていても、「もしかしたら」という期待を捨てきれずに宝くじを買ってしまうのと同じです。
合理的に考えれば間違った行動かもしれません。ですが、「可能性があるなら夢を見てもいいじゃないか」というのが人間の本能なのだと思います。
非効率だと分かっていながらも、逆にこの非効率性を受け入れた方が、かえって良い結果に繋がることもあるのではないかと私は考えています。
本書にも、興味深い話が紹介されていました。
インデックス投資の第一人者であるバートン・マルキール氏とチャールズ・エリス氏でさえ、新興国株などのアクティブ運用を行っており、「完璧な人間はいない」と語っているそうです。インデックスファンドを世に広めた彼らが、現実にはアクティブ運用をしていたという事実は、非常に示唆に富んでいます。
また、本当かどうかは定かではありませんが、こんな逸話もあります。
効率的市場仮説で有名な経済学者ポール・サミュエルソンが、集中投資とバリュー投資で知られるウォーレン・バフェットの投資会社、バークシャー・ハサウェイの株を保有していたという話です。これが本当なら、彼らは自分が提唱する理論と矛盾する行動を取っていた可能性があることを意味します。
このように、「もしかしたら」という可能性に抗えないのが人間です。 その本能をよく理解しているからこそ、この本の筆者も、そして私もコア・サテライトという投資法にたどりついたのかもしれません。
この本こそが、「お金の名著」?
実践する中で、具体的な投資方法に関しては人それぞれのものになるのかもしれません。
ですが、この『お金の名著200冊を読破してわかった!投資の正解』には、投資の考え方のエッセンスが凝縮されていると感じました。
どんな投資手法を選ぶにせよ、その土台となる哲学的な考え方は非常に重要です。
また、本書の中には投資の理論の他にも、投資における「マイルール」の重要性についても触れています。
実は私にとっても、この「マイルール」は投資の核心だと言っても過言ではありません。
損する得するといった、お金を動かす行為は、非常に感情を揺さぶられやすいものです。その中で、ルールがなかったら、感情に振り回されてしまい、結果的に誤った判断を下す可能性が極めて高くなります。
だからこそ、どんな時でもこのマイルールを守り抜くという強い意志が必要になってきます。
本書には、「感情に支配されてしまうと、自分が決めたルールを疑問視するのではなく、単純に忘れてしまう」という、ハッとさせられる言葉が載ってました。
ルールを見失った時、人はとんでもない失敗を犯してしまうという事実を、深く心に刻み込む必要があります。
そして、このルールは単に合理的なだけでなく、自分の心理的な反応も考慮に入れることで、より効果を発揮するという点にも触れられています。
まとめるなら、この本のすべての項目が投資するにあたって重要なものなのだと思います。まさに、投資の核心となるエッセンスが凝縮された一冊だと感じました。