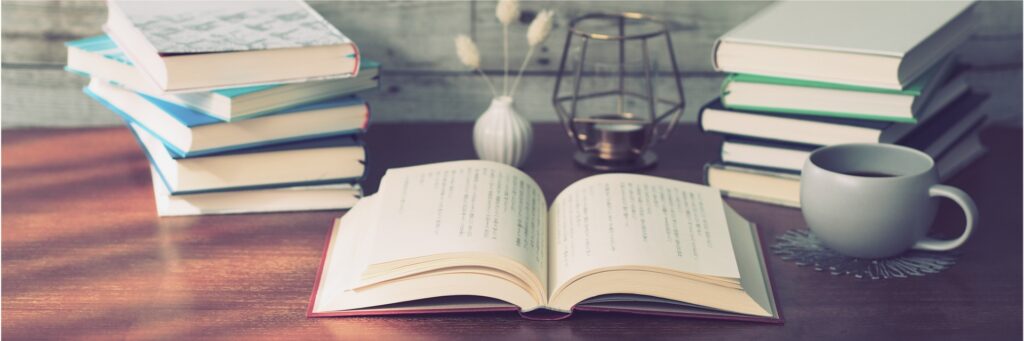
読解力こそが、最強のスキル?
『シン読解力: 学力と人生を決めるもうひとつの読み方』 新井 紀子 (著)
「本をたくさん読んでいる」からと言って、文章を理解する能力があるとは限らない。
今回の本『シン読解力』の著者が書いた、『AI vs 教科書が読めない子どもたち』、それとそれに続く『AIに負けない子どもを育てる』(東洋経済新報社)は衝撃的な内容でした。
この「文章を理解して読めていない」という話には、思い当たる節が多々あります。
普段の生活でも、メールの意図をうまく読み取れなかったり、自分の書いた文章が相手に伝わらなかったりする経験はありませんか?
これは、文章をしっかりと読めていないことによる問題なのかもしれません。
本書の中でも、この文章を読んで理解する読解力を測る問題がいくつか登場してきますが、その問題すべてに正解することができる人は、むしろ少ないのではないかと思われます。
文章を読んで、その内容をしっかり理解するというのは、思っている以上に高度なスキルが必要なのかもしれません。
読んでいるつもりでも、本当の意味では全く読めていない。
しかも、本人は読めているつもりでいるから、なおさらたちが悪い。
本書の中でも触れていますが、世間一般で言う「勉強ができない」には、そもそも教科書の文章を読んで理解することができていないことから始まっている可能性があると考察しています。
過去を思い起こせば、学校に通っていた時代に、大して勉強をしてるわけでもないのに、とても良い成績の人がいたり。資格試験の勉強で、練習問題をあまり解かなくても、テキストを読むことで、合格点を取ってしまうような人がいたりする。
彼らの頭の良さは、この読解力に違いがあるということなのかもしれない。
著者が開発した「RST(リーディングスキルテスト)」というテストをつかって、50万人のデータを取り、この読解力の違いによって、社会においてどんな違いがみられるのかを考察しているのが、本書『シン読解力』です。
この本の通りならば、この『シン読解力』というスキルは、大学受験、社会生活、仕事、生活、様々な面でとても重要なスキルであることがわかります。
たくさんの文章に囲まれ、たくさん目にしているのに、理解して読むことはできていない?
今はスマホやパソコンがとても身近なものとなり、ウェブから様々な情報が文字で入ってきます。ニュースサイトやSNS、文字や文章を見ることが、スマホなどが普及する以前よりも、ずっと増えていると感じています。
しかし、たくさんの文字や文章を見ていることで、文章を理解する能力が上がっているのかというと、そういうわけでないようです。
スマホなどから入ってくる情報に対しては、文章の中にあるキーとなる単語を拾って、なんとなく意味を理解しようとすることがあります。つまり文章をしっかり読むのではなく、いわゆるななめ読みをすることで効率よく大量の情報を得ようとする傾向があると、自分でも実感しています。
そのため、しっかり読めばわかることも、そのしっかり読むこと自体ができていなかったりする。
実際にRSTの問題を解いてみると、すべての答えが読めばわかる事なので、答えがわかった時は、なぞなぞの答えを知った時のように「そういうことか!」と感じることが多いです。
難しいわけではないのかもしれないけれど、なぜか難しい。文章とは、これほど難しいものだったのかと、感じさせられます。それと共に、この読解力の大切さをひしひしと感じます。
この本で筆者も言っているように、子供たちには、下手な塾に通って学力を上げようとする以前に、この本の言うところの「シン読解力」を身に付けることの方が先なんだろうと感じます。
現代のテストやプリントにあるような、文章を読むのではなくキーポイントを探して回答する、似たような問題の傾向をつかんで答えを導く。これでは文章をしっかり読んで理解するという事ができていません。
その結果、学年が上がるにつれて教科書を読んで理解することに苦痛を感じ、勉強もできなくなっていく。
そしてさらに問題となるのが、私たちが普段スマホなどから得ようとする、こういうポイントだけ抜き出すようなやり方は、まさにAIの得意とするところだという事です。
つまり、『AI vs 教科書が読めない子どもたち』の話に立ち返れば、このようなAIと同じような方法で学習をしていたら、本当に近い将来AIに仕事を奪われることにもなりかねません。
シン読解力はスキルであり、訓練すれば身に付けることができる
RSTで好成績を挙げられるような人は、学力も高く、有名な大学に入学する傾向がある。また、高度な仕事をする職に就き、高い収入を得ている傾向もみられる。
RSTで好成績を上げられるような人になるためにどうしたらいいのだろうか。もしくは、RSTの成績が良いのは、天才的なもので、訓練して身に付けられるようなものではないのかどうか。
それが、本書「シン読解力」のポイントになっています。
結論から言えば、「シン読解力」は、後からでも身に付けることができることが分かったと言います。そして、どうやって訓練すればいいのかも、50万人のデータからわかったという話です。
これは、ちょっと嬉しい話だと感じました。
そうはいっても、この本で「シン読解力」と呼んでいるものがどういうものなのか、もしかするとこれは、この本を読んでみないとピンとこないものなのかもしれません。
「本をたくさん読んでいるし、読解力は十分あるつもりだ」と思っている人もいるかもしれませんが、ところがどっこいそうでもないことに気づいたとき、読解力の大切さとその意味の深さを実感することになると思います。
私も、いろいろな本を読んできたつもりでいました。その中でも口語調で書かれていない本。とくに海外の人が書いた本を翻訳した本を読むと、読むのが途端に遅くなる傾向があるなと感じています。
その理由がなぜなのか、本書ではっきりとわかりました。
そしてもしかすると、その読みにくいと感じている本の内容も、本当のところは全然理解できていない可能性があるかもしれないとも感じました。
「シン読解力」、このスキルは、ぜひとも身に付けたいスキルだと思いました。