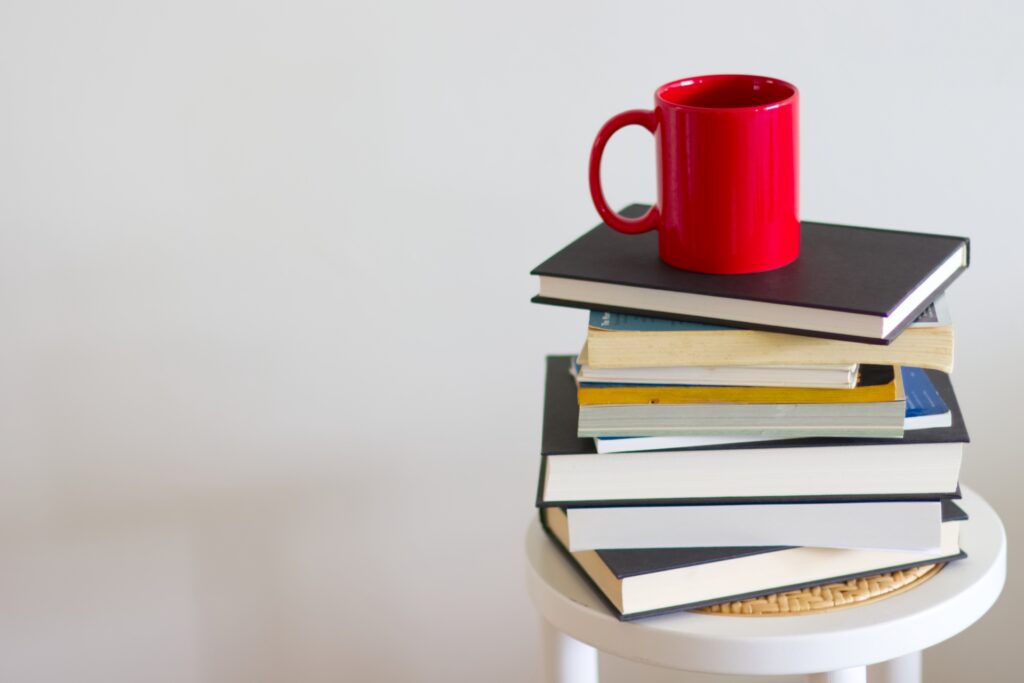
ウォーレン・バフェットのようになりたい!
『史上最強の投資家 ウォーレン・バフェット: 資産1260億ドルへの軌跡』 トッド・A・フィンクル (著)
バフェットは「投資の神様」か、それとも「偉大な起業家」か?
ウォーレン・バフェットといえば、世界長者番付の常連であり、「投資の神様」として知られています。
しかし、本書を読むと、バフェット氏の成功の根源には、幼少期から培われた起業家精神があることが強く印象づけられます。
彼は単に企業の株を買う投資家ではなく、企業そのもののオーナーシップに深く関わり、長期的な視点でその価値を高めてきた「起業家=経営者」としての側面を高く評価しているのが本書の特徴です。
著者は、バフェット氏の家族、生い立ち、そして盟友チャーリー・マンガー氏との関係性といった人間的な側面に光を当て、彼がいかにして現在の投資哲学を築き上げたのかを探ります。
投資手法の解説書というよりは、「バフェットという人物から何を学ぶか」を追求した一冊です。
年収5,600万円で満足?バフェットが証明する「お金よりも大切な価値観」
世界有数の大富豪であるバフェット氏ですが、彼の収入と資産に関する事実は、多くの個人投資家に衝撃を与えます。
- バークシャー・ハサウェイから受け取る年収は、長年年10万ドルで維持されています。その他の収入が約30万ドルあるといわれていますが、それと合わせても、日本円で約5,600万円程度です(1ドル140円換算)。
- 彼の資産の大半は、配当金を出さないバークシャー・ハサウェイの株式です。彼はこの株を売却しないため、手元に入る現金収入は、資産額の大きさとは無関係に上記程度の額にとどまります。
- さらに彼は、死後の遺産のほぼすべてを慈善団体へ寄付すると宣言しています。
世界トップクラスの億万長者でありながら、「自分にとって十分な収入があれば、それ以上のお金は必要ない」というバフェット氏の価値観が鮮明に浮かび上がります。
本書の本当の目的は、この「倹約家」で「質素」な投資家の生き方から、私たち一般の個人が「幸せに生きるためのヒント」を見つけ出すことにあります。
投資は「アート」である:割引キャッシュフロー法と失敗の教訓
バフェット氏のような偉大な投資家になるための具体的なヒントも、もちろん本書には含まれています。
彼の投資手法として有名なのが、企業の将来的なキャッシュフローを現在価値に割り引いて企業価値を評価する「割引キャッシュフロー法(DCF法)」です。本書でもこのDCF法について解説をしています。
しかし、著者は、この理論をマスターしたとしても、バフェット氏と同じパフォーマンスを出すことは「現実的に不可能」だと示唆します。
なぜなら、投資は単なる理論ではなく、「アート(芸術)」のようなものだからです。
- 企業や市場の評価には、感性や洞察力の影響が強く出る。
- そして、何よりも「運」が大きな要素を占める。
本書では、バフェット氏が子供の頃や、大人になってから株式の売買で失敗した経験についても紹介されています。
その多くが、一度買った株を長く保有することが大切だと理解しながらも、人間的な感情や判断ミスによって売却し、後で大きな利益を逃したというエピソードです。
後から振り返らなければ、その判断が「成功」か「失敗」かはわからない。
だからこそ、投資は理論だけでは割り切れない「アート」であり、最高のパフォーマンスを追うことだけが全てではないのです。
【お金のいろは 運営からの提案】
ウォーレン・バフェット氏から学ぶべきは、「資産運用の哲学と価値観」です。
貴方が目指す「投資で幸せになる」という目標は、いくらの資産を持つかではなく、どのような目的で資産を築くかによって決まります。
お金のプロであるファイナンシャルアドバイザーは、お客様一人ひとりの「幸せの価値観」に基づいた、無理のない資産形成計画をサポートします。バフェット氏の哲学を、あなたの人生に落とし込む具体的な方法を知りたい方は、ぜひご相談ください。
👇 バフェットに学ぶ「資産運用の哲学」をあなたの人生に活かす ⇒ [マネー講座・無料相談はこちらから]