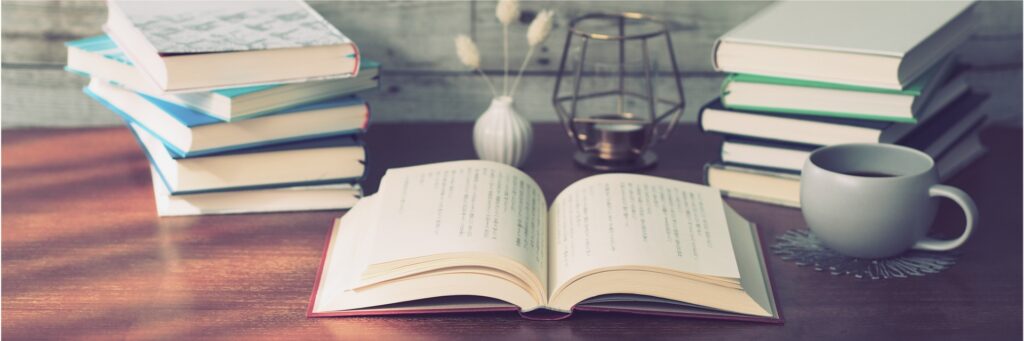
アセットアロケーションとオルタナティブ投資
『投資に必要なことはすべて海外投資家に学んだ』 シデナム 慶子 (著)
なぜ「海外投資家」の戦略が、私たち個人投資家に最適なのか?
近年、「S&P500」や「オルカン」といった株式100%のインデックス投資が最適解とされがちです。
しかし、その戦略を個人が数十年単位の超長期で感情に左右されずに続けられるでしょうか?
本書が提唱しているのは、株式市場の短期的な変動に惑わされない、より堅実で確実性の高い「アセットオーナー」の運用戦略です。
アセットオーナーとは?
本書でいう「海外投資家」、すなわちアセットオーナーとは、大学の基金や財団など、莫大な資金を超長期で運用する機関を指します。
日本で最も身近な例は、私たちの年金資産を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)です。
これらの機関の運用目的は、以下の点で私たち個人の資産運用と極めて似ています。
- 超長期の視点: 数年ではなく、数十年の単位で資産を増やし続けることが最重要。
- 柔軟性: 状況が芳しくない時期には投資を控えたり、資産配分を調整したりする自由度がある。
一般的な投資信託(例:日本株投信)が、集めた資金を決められた資産に100%投資し続けなければならないのに対し、アセットオーナーや個人投資家は、「資産配分(アセットアロケーション)」をコントロールできる点で共通しているのです。
運用の成否を分ける「アセットアロケーション」の絶大な効果
アセットオーナーの運用戦略の根幹にあるのが、分散投資と資産配分(アセットアロケーション)のコントロールです。
たとえばGPIFは、国内・海外の債券と株式にそれぞれ約25%ずつ投資する(2024年度)など、複数の資産に分散投資することで、リスクを管理しつつ、安定的なリターンを目指しています。
確かに、過去のデータだけを見れば、「オルカン」などの株式100%投資が最高のパフォーマンスを出しています。しかし、そのリターンを追うあまり、暴落時に人間の感情(恐怖)に負けて「売却」してしまえば、長期的な成功は望めません。
感情をコントロールする投資戦略
著者は、「感情」こそが相場変動の最大の要因であり、個人が投資で失敗する最大の原因だと指摘します。
そのため、最高のリターンを追うよりも、リスクをコントロールしながら運用を行うアセットアロケーション戦略こそが、個人が長期で成功するための最適な方法であると結論づけています。
一般的な家庭の資産形成であれば、年率3%~5%程度のリターンでも、月3万円を40年間積み立てれば2,700万円を超える(年利3%で計算)資産形成が可能です。
つまりは、株式に100%投資して高いリターンを追わなくても、十分な資産形成は可能なのです。
個人の資産運用のフロンティア「オルタナティブ投資」
本書のもう一つテーマに挙げているのが「オルタナティブ投資」です。
ハーバード大学やイエール大学といった一部の大学基金や年金基金では、すでにプライベートクレジットや不動産などのオルタナティブ資産(株や債券といった伝統的資産以外の投資先)を積極的に組み入れています。
これらの資産は、市場との相関性が低いものが多いため、ポートフォリオ全体の安定性を高める効果が期待されています。
個人がオルタナティブ投資に興味を持つべき理由
これまで、オルタナティブ投資は最低投資金額が非常に高く、個人投資家には手の届かないものでした。
本書の著者は、このオルタナティブ投資を一般の個人投資家が利用できるようにすることを目指した金融機関のCEOでもあります。
個人の資産運用がアセットオーナーの戦略に倣うのであれば、その投資の範囲も広げ、オルタナティブ投資にも関心を持ってみてはどうだろうかと著者は提案しています。
オルタナティブ投資はともかく、個人投資家にとってはアセットアロケーションを考えることこそが、資産運用の中心だという考え方には、私個人も同感です。
【お金のいろは 運営からのお知らせ】
感情に左右されない長期的な資産運用は、将来の老後資金(年金・貯蓄)の不安を解消する最も確実な方法です。
貴方の現在の資産状況や目標に応じた最適なアセットアロケーションや、投資の疑問について、専門のファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。
👇 個人の資産運用戦略についてプロに相談する ⇒ [マネー講座・FP相談はこちらから]